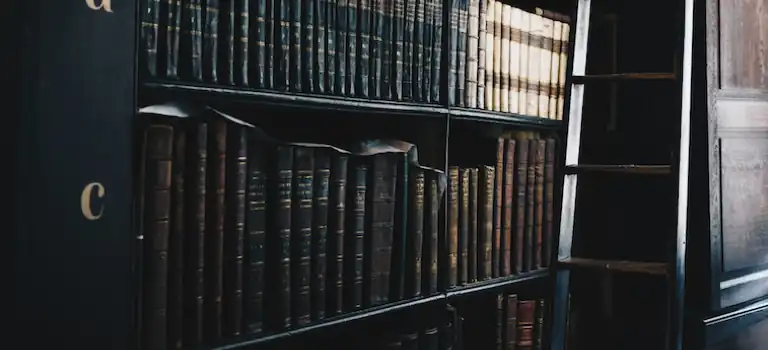改正貨物自動車運送事業法の重要ポイント完全ガイド
改正の背景と全体像
貨物自動車運送事業法の改正は、運送事業における取引関係の適正化と、委託先事業者の健全な事業運営を確保することを目的としています。特に、多重下請構造における不透明な取引慣行を是正し、適正な運賃・料金の収受を実現するための制度が整備されました。
改正の3つの柱
今回の改正では、①書面交付義務、②健全化措置、③実運送体制管理簿の3つが新たに規定されました。これらは相互に関連し、運送事業の透明性向上と適正化を実現する仕組みとなっています。
改正のポイント
- 運送契約における書面の相互交付を義務化
- 委託先事業者の健全な運営を確保するための措置の実施
- 実運送体制の可視化による下請構造の把握
書面交付義務の詳細
真荷主との契約(第12条関係)
真荷主(自らの事業に関して運送を委託する者で、貨物自動車運送事業者以外のもの)と貨物自動車運送事業者が運送契約を締結する際、以下の内容を記載した書面を相互に交付しなければなりません。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 運送の役務の内容 | 運送する貨物の種類、運送区間等 |
| 運送の対価 | 運賃の金額及び算出方法 |
| 附帯業務の内容・対価 | 荷役作業等が含まれる場合の内容と料金 |
事業者間の利用運送(第24条関係)
貨物自動車運送事業者等が他の事業者の行う運送を利用する場合にも、同様に書面交付が義務付けられます。以下の4つのケースが対象となります。
- 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の運送を利用する場合
- 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の運送を利用する場合
- 第一種貨物利用運送事業者(下請構造内)が一般貨物自動車運送事業者の運送を利用する場合
- 第一種貨物利用運送事業者(下請構造内)が他の第一種貨物利用運送事業者の運送を利用する場合
健全化措置の実施
健全化措置とは、委託先事業者の健全な運営を確保するために講ずべき措置のことです。運送を利用する事業者は、委託先が適正な運賃・料金を収受できるよう、様々な取組を実施する必要があります。
努力義務(第24条第1項)
貨物自動車運送事業者等が他の事業者の運送を利用する際、委託先の健全な運営を確保するための措置を講ずるよう努めなければなりません。これは以下の3つのケースに適用されます。
- 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の運送を利用する場合
- 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の運送を利用する場合
- 第一種貨物利用運送事業者(下請構造内)が一般貨物自動車運送事業者の運送を利用する場合
具体的な健全化措置の内容
1. 事前の費用聴取と定期的な協議
あらかじめ委託先から運送に要する費用の概算額を聞き取り、それを勘案して利用の申込みを行います。継続的な取引については、少なくとも一定期間ごとに取引条件について話し合う場を設け、物価変動等を踏まえた見直しを申し出やすい関係を構築します。
2. 荷主への交渉
委託先に適切な運賃・料金を支払えるよう、荷主への交渉を行います。特に物価変動等を踏まえた見直しの申出があった場合は、その根拠を確認した上で、適切に転嫁されるよう荷主と交渉します。
3. 契約条件の明確化
運送契約に、再委託の制限(原則として再々委託を行わない等)や、再委託を行う場合の健全化措置の実施等の条件を盛り込みます。
4. 実運送体制の確認
元請事業者の場合、実運送体制管理簿を通じて委託が二次請けまでとなっているかを確認し、条件が遵守されていない場合は改善を求めます。
5. その他の取組
パートナーシップ構築宣言に基づく取組等、委託先との取引関係の適正化に資する取組を実施します。
重要なポイント
健全化措置は、委託先事業者との信頼関係を構築し、持続可能な物流体制を確保するための取組です。単なる法令遵守ではなく、パートナー企業との共存共栄を目指す姿勢が求められます。
実運送体制管理簿の作成・保存
貨物自動車運送事業者(一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者)は、真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の事業者の運送を利用した場合、実運送体制管理簿を作成・保存する義務があります。
作成義務の対象
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 対象事業者 | 一般貨物自動車運送事業者 特定貨物自動車運送事業者 |
| 対象貨物 | 真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物 |
| 作成時期 | 他の事業者の運送を利用したとき |
| 保存期間 | 運送完了日から1年間 |
| 保存場所 | 営業所 |
記載内容
実運送体制管理簿には、以下の情報を記載します。
- 実運送事業者の商号又は名称
- 実運送事業者の許可番号等
- 運送を行った区間
- その他必要な事項
運送利用管理規程と運送利用管理者
一定の規模以上の貨物自動車利用運送を行う事業者は、運送利用管理規程を定め、運送利用管理者を選任し、国土交通大臣に届け出る必要があります。
対象事業者
特別一般貨物自動車運送事業者・特別特定貨物自動車運送事業者
一定の規模以上の貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者を「特別一般貨物自動車運送事業者」、特定貨物自動車運送事業者を「特別特定貨物自動車運送事業者」といいます。
運送利用管理規程の内容
運送利用管理規程には、健全化措置の実施に関する以下の事項を定めます。
第一章:総則
目的、適用範囲等の基本事項
第二章:健全化措置を実施するための事業の運営の方針等
基本方針、重点施策等
第三章:健全化措置の内容
具体的な措置の内容(費用聴取、荷主交渉、契約条件、実運送体制の確認等)
第四章:健全化措置の管理体制等
社内組織、運送利用管理者の選任・解任・責務、教育・研修、内部監査等
運送利用管理者の責務
- 全社員への法令遵守と委託先との優良な関係構築の意識徹底
- 健全化措置の実施に関する事業運営方針の決定
- 実施及び管理体制の整備
- 定期的及び随時の内部監査の実施と取締役会への報告
- 実運送体制管理簿の作成事務の監督
- 必要な改善措置の実施
- 社員への教育・研修の実施
- 健全化措置の統括管理
届出の手続き
運送利用管理規程を作成(変更)した場合、及び運送利用管理者を選任(解任)した場合は、それぞれ所定の様式により国土交通大臣(地方運輸局長経由)に届け出る必要があります。
実務対応のポイント
書面交付の実務
- 運送契約書のフォーマットを整備し、必要事項が漏れなく記載されているか確認
- 荷役作業等の附帯業務がある場合は、その内容と対価を明確に区分して記載
- 電磁的方法で提供する場合は、事前に相手方の承諾を取得
- 書面の保管・管理体制を整備(契約書の控えを適切に保管)
健全化措置の実践
- 委託先との定期的な協議の場を設定(四半期に一度等)
- 物価上昇等の転嫁交渉がしやすい関係構築
- 荷主との交渉記録の作成・保管
- 契約条件に再委託の制限等を明記
管理簿の作成・保存
- 実運送体制管理簿のフォーマットを作成
- 1.5トン以上の貨物について、利用運送を行った場合は必ず記録
- 運送完了日から1年間、営業所に保管する体制を整備
- 定期的に管理簿を確認し、二次請けまでとなっているかチェック
社内体制の整備が重要
法改正への対応は、単なる書類作成だけでなく、社内の意識改革と体制整備が不可欠です。運送利用管理者を中心に、全社員が委託先との適正な取引の重要性を理解し、実践できる体制を構築しましょう。
まとめ
改正貨物自動車運送事業法は、運送業界における取引関係の適正化と、持続可能な物流体制の構築を目指すものです。書面交付義務、健全化措置、実運送体制管理簿の3つの柱を通じて、多重下請構造の透明化と適正な運賃・料金の収受を実現します。
特に重要なのは、これらの取組が単なる法令遵守ではなく、委託先事業者との信頼関係構築と共存共栄を目指すものであるという認識です。運送利用管理規程の整備と運送利用管理者の選任を通じて、組織全体で健全化措置に取り組む体制を構築することが求められます。
実務対応では、書面の整備、定期的な協議の場の設定、荷主への交渉、管理簿の適切な作成・保存等、具体的な行動が必要です。社内の意識改革と体制整備を進め、法改正の趣旨を理解した上で、着実に対応を進めていきましょう。