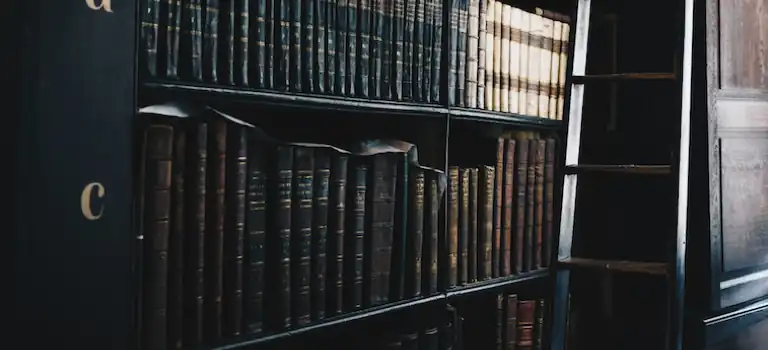改正貨物自動車運送事業法 Q&A
このページについて
令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」は、令和7年4月1日から施行されます。
このページは、改正貨物自動車運送事業法に関する国土交通省がお寄せいただく問合せの中から、主なものをQ&A形式でまとめたものです。事業の改正内容への対応にあたっての参考としてご活用ください。
令和7年3月31日時点
【1. 総論】改正の概要と基本的な定義
従前より貨物自動車運送業においては、多重下請構造や口頭による運送契約の締結等が、適正な運賃・料金の収受に当たっての大きな課題となっていました。そうした課題に対応するため、今般、トラック法を改正し、
- 運送契約締結時等の書面交付義務
- 下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務
- 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務
などの規制的措置を導入することとしております。各改正事項の概要については、別紙1をご参照ください。
令和7年4月1日より施行されます。
改正トラック法上の真荷主とは
- 自らの事業に関して
- 貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、
- 貨物自動車運送事業者以外のもの
をいいます。「自らの事業に関して」とありますので、一般消費者は真荷主には含まれません。改正トラック法上の元請事業者は「実運送体制管理簿を作成する貨物自動車運送事業者(※貨物軽自動車運送事業者を除く)」を指します。利用運送事業者はここには含まれません。実運送体制管理簿の作成主体については、問4-2をご参照ください。
自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、個人事業主であっても「真荷主」に該当します。
引越自体は当該法人の事業ではないため、該当しません。ただし、オフィスの移転を貨物利用運送事業者に委託し、当該貨物利用運送事業者が他の貨物自動車運送事業者に運送委託した場合は、当該貨物利用運送事業者が真荷主に該当することになります。
「真荷主」に該当する場合には、改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付義務が課されることになります。自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、運送の役務の内容及び対価(運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を、当該貨物自動車運送事業者との間で相互に交付しなければなりません。具体的な記載事項等は【2. 書面交付関係】をご参照ください。なお、交付した書面についてはその写しを1年間保存することとされています。また、真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧・謄写の請求をすることができます。
【2. 書面交付関係】運送契約の書面交付義務
真荷主及び貨物自動車運送事業者(※1)が運送契約を締結するときは、改正トラック法第12条第1項に基づき、相互に所定の事項を記載した書面を交付することとなります。貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するとき(※2)は、改正トラック法第24条第2項に基づき、委託元から委託先に対して所定の事項を記載した書面を交付することとなります。
※1 特定貨物自動車運送事業者を除く。
※2 具体的には以下の4通りの場合に適用される:
- 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
- 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
- 第一種貨物利用運送事業者(下請構造の中にいる場合に限る。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
- 第一種貨物利用運送事業者(下請構造の中にいる場合に限る。)が他の第一種貨物利用運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
交付書面には以下の事項(以下「法定事項」という。)を記載する必要があります。
- 運送の役務の内容及び対価
- 運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合には、その内容及び対価
- その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージなど)
- 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所
- 運賃・料金の支払方法
- 書面の交付年月日
荷役作業や附帯業務は原則として「運送の役務以外の役務」に該当するものと考えられます。他方で、例えば宅配便における玄関先への配達など、取引の実態として、委託者・受託者がともにその作業が運送の一部をなすものとして認識しており、かつ当該作業に係る対価を運賃に包含させることに両者間で異論がない場合には、当該作業を「運送の役務」として取り扱うことは差し支えありません。
時間制運賃の場合、その時間内に行われる積込み・取卸しに係る対価を運賃に包含させることは問題ありません(別建てする必要はありません)(※)が、その場合でも、積込み・取卸しが発生する旨は書面に明記しなければなりません。
※ 国土交通省がお示ししている「標準的運賃」では、時間制運賃の場合、その時間内であれば、待機時間料や積込料・取卸料は時間制運賃の中に包含されております。
具体的にどのような作業を行う必要があるのかを委託先が認識できるのであれば、特に記載の粒度は問いません。
運送契約締結時に未定の事項がある場合(例えば附帯業務の有無など)、当該事項以外の事項について書面交付を行い、後日内容が決定した時点で、その内容について記載した書面を別途交付するという対応をとることについては問題ありません。この場合、当初交付した書面(以下「当初書面」という。)と後日交付した書面(以下「後日書面」という。)の関連性を確認できるようにしておく必要があります。また、後日交付する書面については、遅くとも運送が行われる前には交付しなければなりません。
後日書面の交付をもって書面交付義務が完全に履行されたものと考えられますので、当初書面も含めて、後日書面を交付した日から1年間保存する必要があります。
運送に伴い生じる費用について、委託者が実費を負担することとしている場合、例えば「運送に要した有料道路利用料、○○料、△△費については、実費を委託者が負担する」旨の記載があれば、当該費用に係る料金については具体的な金額が記載されていなくても問題ありません。
実際に要した有料道路利用料について改めて書面を交付する必要はありませんが、運賃・料金等について変更が生じた場合の取扱いについては、運送契約の締結時にあらかじめ取り決めておくことが望ましいです。
必要な事項が記載された書面であれば、特に書面の形態・様式等は問いませんので、送り状等を交付書面として活用いただくことも可能です。交付書面の一例を次頁に掲載しますので、参考にしてください。
法定事項が基本契約書で網羅されていれば、日々の運送依頼について書面交付は不要ですが、例えば、附帯業務の有無が運送ごとに異なり、各運送依頼時にその有無が確定するような場合には、それぞれの運送依頼ごとに当該附帯業務の有無等について記載した書面を交付する必要があります。
電話で運送依頼を行う場合でもあっても、電話連絡後直ちに書面を交付しなければなりません。なお、電話連絡のみによる運送依頼は、書面交付義務違反となります。
問1-3のとおり、一般消費者は「真荷主」には含まれないため、一般消費者と運送契約を締結する際に書面交付義務はかかりません。
「災害その他緊急やむを得ない場合」又は「真荷主が郵便物・信書便物の運送を委託する場合(※改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付に限る)」には書面交付義務の対象外となりますが、それ以外の場合については基本的に書面を交付する必要があります。
該当しません。スポット輸送についても、災害時等を除き、基本的に書面を交付する必要があります。
「真荷主」に該当する第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者は、改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付義務の対象となります。真荷主の定義については問1-3をご参照ください。また、下請構造の中にいる(※1)第一種貨物利用運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合には、第24条第2項に基づく書面交付義務の対象となります。
(※1) 「下請構造の中にいる」とは、問2-1図1<パターン3>における貨物利用運送事業者のように、自身より上流に貨物自動車運送事業者が存在している場合を指す。
当該事業者が第一種貨物利用運送事業者に該当する場合は、問2-15のとおり書面交付義務の対象となります。第一種貨物利用運送事業者に該当しない場合は、当該事業者が「真荷主」に該当する場合に、改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付義務の対象となります。
改正トラック法による書面交付は、運送契約を締結する当事者間で行うこととなるため、貨物自動車運送事業者が、マッチングサービス事業者を介してマッチングした他の貨物自動車運送事業者と直接運送契約を締結する場合、当該他の貨物自動車運送事業者に対して書面を交付することとなります。この場合において、実務上マッチングサービス事業者を経由して書面交付を行うことも否定はされませんが、仮に委託先に書面が到達しなかった場合や記載事項に不備があった場合などは、一義的には書面の交付主体たる貨物自動車運送事業者に義務不履行の責任が生じ得ることになるため、利用するマッチングサービス事業者が改正トラック法の改正内容に対応しているかどうかをあらかじめ確認しておくことが有効です。他方で、マッチングサービス事業者が第一種貨物利用運送事業者であって、貨物自動車運送事業者が当該マッチングサービス事業者と運送契約を締結する場合は、当該マッチングサービス事業者に対して書面を交付することとなります。
罰則はありませんが、貨物自動車運送事業者についてはトラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。また、荷主についてもトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性があります。
お尋ねのような書面のやり取りをもって相互交付したものと取り扱っていただいて差し支えありません。また、委託先の貨物自動車運送事業者の「名称及び住所」についても同様に、真荷主が交付する申込書において記載が無くとも、委託先の貨物自動車運送事業者が受け取った書面に自社の「名称及び住所」を追記して荷主に交付すれば、相互交付したものと取り扱っていただいて問題ありません。この取扱いをした場合、真荷主は、委託先から交付のあった書面又はその写しを交付のあった日から1年間保存する必要があります。なお、改正トラック法第24条第2項に基づく書面交付については、上記のような取扱いは認められず、委託者から委託先に対して法定事項が網羅された書面を交付する必要があります。
契約の相手方から承諾を得ている場合、書面(紙媒体)の交付に代えて、電子メール等の電磁的方法により法定事項の提供を行うことが可能であり、例えば、以下のような方法が挙げられます。
- 電子メールやファックス(※)等による送受信
- ウェブサイト上に表示された記載事項を契約の相手方がダウンロードする方法
- 契約の相手方がログインして閲覧するインターネットページにアップロードする方法
- CD-R等に記録して契約の相手方に交付する方法
なお、電子メールについては、PDF等を添付して送信する方法だけでなく、メール本文に法定事項を記載して送信する方法も可能であり、その際の記載例については次頁をご参照ください。
(※) 電磁的記録をファイルに記録する機能を有するファックス(複合機など)へ送信する方法は「電磁的方法による提供」に該当し、事前に相手方の承諾が必要となるが、受信と同時に書面により出力されるファックスへ送信する方法については「書面の交付」に該当し、事前の承諾等は不要である。
<施行日以降に締結した契約について>
法定事項を変更しようとする場合は、変更のあった事項について、書面の交付を行う必要があります。ただし、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更など形式的な変更をしようとする場合や、法定事項以外の事項を変更しようとする場合は、改めて書面の交付を行う必要はありません。また、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長する場合についても、改めて書面の交付を行う必要はありません。
<施行日より前に締結した契約について>
施行日以降に契約内容を変更しようとする場合は、以下の取扱いとなります。
- 契約締結時に法定事項を満たす書面をすでに交付している場合⇒<施行日以降に締結した契約について>と同様の取扱いとなります。
- 契約締結時に法定事項を満たさない書面を交付している場合⇒変更の内容にかかわらず、法定事項を満たす書面を改めて交付する必要があります。
- 契約締結時に書面交付を行っていない場合⇒変更の内容にかかわらず、法定事項を満たす書面を交付する必要があります。
施行日より前に締結した契約については、改正内容に合わせるためだけに変更や書面交付を行っていただく必要はありませんが、施行日以後に契約内容に何らかの変更が生じる場合については、問2-21<施行日より前に締結した契約について>のとおり取り扱う必要があります。なお、取引環境の改善に向けて、今般の改正を機に契約内容の見直しを行っていただくことを推奨しております。
当該個別契約を締結するに当たっては、書面交付義務がかかり、その書面は法定事項を満たす必要があります。例えば施行日より前に締結した基本契約において運賃・料金の別建てを行っていない場合、施行日以降に個別契約を締結するに当たって、当該個別契約に係る書面において運賃・料金の別建てを行っていただくか、又は基本契約を変更して運賃・料金の別建てを行っていただく必要があります。なお、施行日より前に締結した基本契約についてすでに書面を交付している場合、当該書面の記載事項と施行日以降に交付する個別契約に係る書面の記載事項を組み合わせる形で法定事項を満たすこととする取扱いについては問題ありません。
改正トラック法に基づき交付する書面が印紙税法上の課税文書になるか否かは、当事者間において運送契約の成立を証する目的で作成する文書に該当するか否かにより判断することとなります。この点、契約とは申込みと承諾によって成立するものであるため、契約の申込事実を記載した申込書、注文書、依頼書などは、通常、印紙税の課税対象にはなりません。つまり、改正トラック法第12条第1項又は第24条第2項に基づき、委託元から委託先に対して運送申込書を交付する場合は、基本的に印紙税の課税対象にはなりません(ただし、(※1)に該当する場合は課税対象となる)。他方で、トラック事業者が荷主から貨物の運送を引き受けた際に荷主に交付する文書で、その文書に運送物品の種類、数量、運賃、発地、着地等運送契約の成立の事実を証する事実が具体的に記載され、貨物運送引受けの証としているものは、その文書の標題のいかんにかかわらず、運送に関する契約書として印紙税の課税対象となります(※2)。つまり、改正トラック法第12条第1項に基づき、委託先から委託元に対して例えばP6のような運送引受書を書面で交付する場合、当該引受書は「運送契約の成立を証する目的で作成する文書」に該当し、印紙税の課税対象となります。なお、電子メールやファックス等の電磁的方法による場合には、課税物件は存在しないことになりますので、印紙税の課税対象にはなりません。
(※1) 委託元から委託先に対して運送申込書を交付する場合であっても、例えば契約当事者の間の基本契約書等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書、見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書、契約当事者双方の署名又は押印があるものなどについては、「運送契約の成立を証する目的で作成する文書」に該当し、印紙税の課税対象となります。
(※2) 貨物の運送に関して作成される文書に対する印紙税の取扱いが国税庁ウェブサイトで整理されていますので、参考にしてください。【国税庁ウェブサイトURL】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/11/05.htm
【3. 健全化措置関係】下請事業者の健全な運営確保
貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するとき(※)に、当該他の貨物自動車運送事業者の健全な運営を確保するための措置(健全化措置)を講ずるよう努めることとされています。
(※)具体的には以下の3通りの場合に適用される:
- 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
- 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
- 第一種貨物利用運送事業者(下請構造の中にいる場合に限る。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
改正トラック法第24条第1項において以下の措置が規定されています:
- 利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。
- 自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃・料金が①の概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃・料金について交渉をしたい旨を申し出ること。
- 委託先の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し、例えば「二以上の段階にわたる委託の制限(再々委託の制限)」等の条件を付すこと。
「二以上の段階にわたる委託の制限(再々委託の制限)」については努力義務の一例としてお示ししているものであるため、当該措置に代えて、委託先の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関してその他の条件(問3-4参照)を付すことによって対応していただくことでも問題ありません。
改正トラック法第24条第1項の努力義務の名宛て人(=条件を付す者)をA、Aの委託先の一般貨物自動車運送事業者をB、Bの委託先の一般貨物自動車運送事業者をCとした場合、例えば、「BがAから引き受けた貨物の運送についてCの行う運送を利用するときは、Cの運送に要する費用をBが聞き取る場を設けた上で申込みをすること」等が想定されます。
健全化措置の努力義務については、元請事業者等の主体的な取組を促すためのものであるため、罰則や行政処分は設けておりません。他方で、運賃・料金を不当に据え置くなど、違反原因行為をしている疑いがあると認められる事業者については、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。
健全化措置の実効性を高めるため、一定規模以上の貨物自動車利用運送を行う貨物自動車運送事業者については、
- 健全化措置の実施に関する「運送利用管理規程」を作成し、国土交通大臣に届け出る義務
- 健全化措置の実施・管理の体制を確保するための「運送利用管理者」を選任し、国土交通大臣に届け出る義務
が課されます。
「前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量(以下「利用運送量」という。)が100万トン以上」である一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者が、運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務の対象となります。貨物利用運送事業者は義務付けの対象にはなりません。
毎年国土交通省にご提出いただいている貨物自動車運送事業実績報告書の「輸送トン数(利用運送)・全国計」の欄に記入された数値にてご判断ください。
国からの指定や通知等はありませんので、各事業者において前年度の利用運送量の確認を確実に行っていただき、100万トン以上である場合には、運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任及び国土交通大臣への届出を行う必要があります。
令和6年度以降に利用運送量が100万トン以上となった場合に義務付けの対象となります。令和5年度以前の利用運送量は問いません。なお、一度運送利用管理規程・運送利用管理者の届出を行っていただければ、翌年度以降改めて届出を行っていただく必要はありません(※変更がある場合には変更の届出が必要)。例えば、届出を行った後に一度100万トンを下回り、その後再び100万トン以上となった場合、過去に一度届出を行っていれば、再度の届出は不要です。
運送利用管理規程に定める事項として、改正トラック法第24条の2第2項において以下の事項が規定されています。
- 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
- 健全化措置の内容に関する事項
- 健全化措置の管理体制に関する事項
- 運送利用管理者の選任に関する事項
運送利用管理規程のひな形については、別紙2をご参照ください。
改正トラック法第24条の3第1項において、運送利用管理者は「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」のうちから1人選任することとされています。
改正トラック法第24条の3第2項において以下の職務が規定されています。
- 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。
- 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。
- 実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。
運送利用管理規程を作成した際には、別紙3の「運送利用管理規程作成届出書」に必要事項を記載し、当該管理規程及び当該管理規程に関し必要な事項を記載した書類を添付の上、主たる事務所を管轄する運輸支局等にご提出ください。
(※運送利用管理規程を変更した際も同様に、「運送利用管理規程変更届出書」及び必要書類を主たる事務所を管轄する運輸支局等にご提出ください。)
また、運送利用管理者を選任した際には、別紙4の「運送利用管理者選任届出書」に必要事項を記載の上、主たる事務所を管轄する運輸支局等にご提出ください。
(※運送利用管理者を解任した際も同様に、「運送利用管理者解任届出書」及び必要書類を主たる事務所を管轄する運輸支局等にご提出ください。)
行政処分の対象となる可能性があります。また、「運送利用管理規程の届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程によらないで、事業を行ったとき」又は「運送利用管理者の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」は、百万円以下の罰金が科されることになります。
【4. 実運送体制管理簿関係】下請構造の把握と管理
真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、貨物の運送ごとに、以下の事項を記載した実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、これを営業所に据え置かなければなりません。なお、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はありません。(詳細は問4-10~問4-10-3をご参照ください。)
【実運送体制管理簿の記載事項】
- 実運送事業者の商号又は名称
- 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
- 実運送事業者の請負階層
真荷主から貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者(※)(=元請事業者)が作成することとなります。
※ 貨物軽自動車運送事業者は除く。
貨物利用運送事業者に作成義務はありませんが、下請構造の中にいる場合には、必要事項を委託先へ通知する義務がかかります。(詳細は問4-6をご参照ください。)
不要です。ただし、真荷主から引き受けた貨物の運送について、一部でも他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用した場合は、作成の対象になります。
元請事業者以外の貨物自動車運送事業者に作成義務はありませんが、必要事項を委託先又は元請事業者へ通知する義務がかかります。(詳細は問4-6をご参照ください。)
真荷主から引き受けた貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象であるとき(=真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、かつその運送の全部又は一部について利用運送を行うとき)、元請事業者は
- (ⅰ)元請事業者の連絡先
- (ⅱ)真荷主の商号又は名称
- (ⅲ)委託先の運送事業者の請負階層
を委託先の運送事業者に対して通知します。なおその際に、当該貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を確実に委託先へ伝達するようにしてください。当該通知を受けた運送事業者は、実運送を行ったときは
- 実運送事業者の商号又は名称
- 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
- 実運送事業者の請負階層
を元請事業者に対して通知し、そこからさらに利用運送を行うときは(ⅰ)~(ⅲ)の事項を委託先の運送事業者に対して通知します。なおその際に、当該貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を確実に委託先へ伝達するようにしてください。以降はこの通知フローの繰り返しとなります。元請事業者は、実運送事業者から通知を受けた①~③の事項を実運送体制管理簿に記録することとなります。
真荷主から運送依頼があった時点で判断します。1.5トン以上の貨物の運送依頼であれば作成対象となり、1.5トン未満であれば対象になりません。実運送の時点で何トン運ぶかや、実運送で混載を行うか等は関係ありません。なお、実重量が把握できない場合は、容積換算重量にて判断いただくことも差し支えありません。
配達先(荷受人)が複数あったとしても、当該運送が一の運送契約に基づき行われる場合には、一度の運送依頼で引き受ける貨物の重量で判断することとなり、お尋ねのケースについては作成義務の対象となります。他方で、配達先(荷受人)ごとにそれぞれ別々の運送契約に基づいて運送が行われる場合には、各運送契約ごとの貨物の重量で判断することとなり、お尋ねのケースについては作成義務の対象とはなりません。
一の運送契約に基づき複数回の運送依頼が行われる場合、それぞれの運送依頼毎の貨物の重量で判断することとなるため、お尋ねのケースについては作成義務の対象とはなりません。
真荷主と元請事業者の間で締結された運送契約の後に締結された運送契約の数でカウントします。つまり、元請事業者の委託先が「1次請け」、「1次請け」の委託先が「2次請け」となり、以降運送契約が締結されるたびに次数が増えていきます。なお、下請構造の中にいる第1種貨物利用運送事業者も運送契約の主体となるため、請負階層にカウントされます。
下請構造の中にいるマッチングサービス事業者が第1種貨物利用運送事業者である場合、当該マッチングサービス事業者は運送契約の主体となるため請負階層にカウントされます。他方で、マッチングサービス事業者が第1種貨物利用運送事業者でない場合、当該マッチングサービス事業者は運送契約の主体とならないため請負階層にはカウントされません。
どの運送について記録されたものであるかが、真荷主及び元請事業者ともに分かる状態であれば、特に記載の粒度は問いません。運送区間を「東京~大阪」のように都道府県単位で記載することや、貨物の内容を「雑貨」や「食料品」のような粒度で記載することも可能です。
系列化等により下請構造が固定化されている場合など、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、当該貨物の運送について、実運送を行う貨物自動車運送事業者やそこに至るまでの委託関係(下請構造)が明らかになっている場合を指します。このような場合、真荷主及び元請事業者はともに実運送事業者とその請負階層についてあらかじめ把握している状態となるため、一度実運送体制管理簿を作成すれば、それ以降に行う当該真荷主に係る貨物の運送については、当該実運送体制管理簿に記録する必要はありません。ただし、委託関係(下請構造)や実運送事業者が異なる運送を行った場合には、当該運送について実運送体制管理簿に記録しなければなりません。
真荷主から貨物の運送を引き受けてから初めて行う運送について実運送体制管理簿を作成してください。それ以降に行う当該真荷主に係る貨物の運送については、「貨物の内容」や「運送区間」等が異なっていても、委託関係(下請構造)や実運送事業者に変わりがない場合は、実運送体制管理簿に記録する必要はありません。なお、最初に記録した運送から1年(※法定の保存期間)を経過した場合は、そこから初めて行う運送について改めて実運送体制管理簿に記録する必要があります。
利用運送先の貨物自動車運送事業者が一者でない場合であっても、貨物の種類や運送区間等に応じて利用運送先を使い分けているなど、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送事業者及びその請負階層が実質的に特定できるような場合には、貨物の運送ごとの記録は要しません。他方で、利用運送先の貨物自動車運送事業者を特定少数に限定していたとしても、荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送を行う貨物自動車運送事業者及びその請負階層が特定されないような場合には、貨物の運送ごとに実運送体制管理簿に記録する必要があります。
前提として、契約を結ぶ時点で、自身がどういった者(貨物自動車運送事業者なのか貨物利用運送事業者なのか)として運送を引き受けるかを明確にしていただくことが基本であると考えており、貨物自動車運送事業者として引き受けた場合は作成義務の対象になり、貨物利用運送事業者として引き受けた場合は作成義務の対象にはなりません。他方で、そういった対応が難しい場合には、荷主より引き受けた貨物の運送について、
- すべて利用運送することがあらかじめ決まっている場合は「貨物利用運送事業者」
- 少しでも自社で運送する可能性がある場合は「貨物自動車運送事業者」
として取り扱っていただくことは否定されないものと考えられます。いずれの場合においても、利用運送を行う際に、例えば「弊社は真荷主に該当するため、御社は元請事業者となります」と伝えるなど、委託先が自身に実運送体制管理簿の作成義務があるのか否かを明確に把握できるようにしてください。
「災害その他緊急やむを得ない場合」には実運送体制管理簿の作成義務の対象外となりますが、それ以外の場合で、真荷主から1.5トン以上の貨物の運送を引き受け、かつその運送の全部又は一部について利用運送を行うときは、基本的に実運送体制管理簿を作成する必要があります。なお、書面交付義務と同様に、単なるスポット輸送については「災害その他緊急やむを得ない場合」には該当しません。
施行日以降に元請事業者が委託先に運送依頼を行ったものから作成する必要があります。例えば、基本契約が施行日より前に締結されている場合であっても、運送依頼自体が施行日以降に行われた運送については、実運送体制管理簿の作成対象となります。
作成期限について具体的な定めはありませんが、運送完了後遅滞なく作成することが望ましいです。なお、例えば一月分をまとめて当該月の末日や翌月初めに作成するという対応をとることについては特に問題ないものと考えられます。
実運送体制管理簿に決まった様式はありませんので、各事業者において作成しやすい形で作成いただいて問題ありません。必要事項が記載されていれば、既存の配車表等も活用いただけます。また、一例として実運送体制管理簿の作成イメージ(図5)を掲載しますので、参考にしてください。
実運送体制管理簿については電磁的記録による作成・保存も可能としているところであり、検索や管理の容易性からも電磁的記録により作成・保存を行うことは有効です。
国に対して定期的な提出等は必要ありませんが、監査やトラック・物流Gメンによる調査等において求めがあった場合は、提出する必要があります。また、真荷主は元請事業者に対して実運送体制管理簿の閲覧・謄写の請求をすることができます。
罰則はありませんが、トラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。
罰則はありませんが、トラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。
通知の不備により実運送体制管理簿が作成できなかった場合、一義的には通知の不備の原因を発生させた者(=通知を滞らせた者)にその責任があると考えられるため、当該者に対して行政処分が行われる可能性があります。他方で、実運送事業者から通知が来なかった場合でも、元請事業者は、実運送事業者及びその請負階層の把握に取り組んでください。
上流の事業者が通知義務を怠る等して通知を受けられなかった場合など下請構造の中にいる事業者が伝達事項を知ることができない場合は、当該事業者に通知義務は課されません(改正トラック法第24条の5第4項ただし書)。この場合、通知義務を怠った上流の事業者に対して行政処分が行われる可能性があります。
【5. その他】その他の改正事項
従前、特定貨物自動車運送事業について、事業の譲渡、合併・分割又は相続(以下「事業譲渡等」という。)が発生した場合、当該事業の権利義務は自動的に承継されることとなっており、権利義務を承継した者は事後の届出義務のみ課されることとされていました。今般、特定貨物自動車運送事業についても、一般貨物自動車運送事業者と同様に事業譲渡等の際に権利義務を承継する者の適格性を審査するために、届出制を認可制とする改正を行いました。これに伴い、特定貨物自動車運送事業について、施行日以降に承継事由が生じる場合は、一般貨物自動車運送事業者と同様に、その事業譲渡等について認可を申請する必要が生じ、認可を受けなければその効力が生じないこととなります。