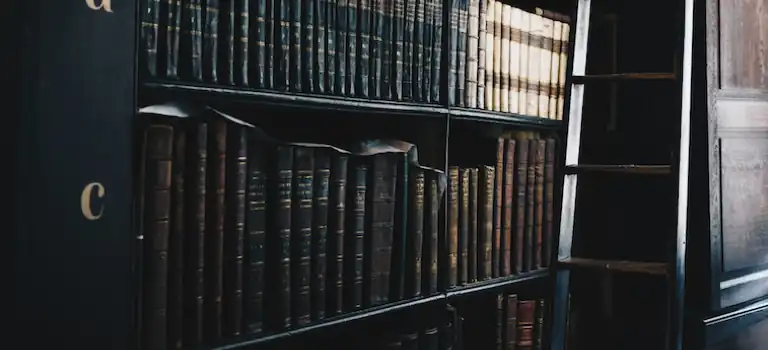貸切バスの運賃料金制度Q&A
①制度全般
Q1. ブロック別運賃料金のブロックの範囲は今後も同じか
A: 原則として2年ごとに運賃・料金制度を見直すこととしており、その際見直す必要があると判断される場合には検討を行う。
Q2. 新たな運賃料金の届出様式は。届出は義務か
A: 届出様式については、各運輸局等に確認されたい。届出は任意だが、届出を行わなかった事業者については改正後の「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の届出及び変更命令の処理要領について」に基づき、変更命令を行うかどうかについて調査を実施する。
Q3. 営業所の所在地により運賃にばらつき、不公平さがあるがどう考えるか
A: 各地域の経済状況や事業者経営状況を勘案して、基準額を算出したものであるため、各地域の実態を反映した運賃と考える。
Q4. 各運輸局で算出された原価でその管内事業者は統一して届出なければいけないのか
A: 新たに公示された運賃・料金は、各地域の経済状況や事業者経営状況を勘案して、基準額を算出したものであるため、基準額に統一して届け出る必要はない。なお、基準額を下回る届出については、改正後の「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の届出及び変更命令の処理要領について」に基づき、変更命令を行うかどうかについて調査を実施する。
Q5. 養護学校、企業送迎などの特殊な運行で、届出運賃を割る場合はどうすればよいか
A: 独自に運賃を算定した上で届出を行い、添付された原価計算書等を基に変更命令を行うかどうかについて調査を実施する。
Q6. スキーバスのような期間限定で、オフ時期の格安運賃は届出できるか
A: 届け出た下限を下回る運賃での運送はできない。
Q7. 既存の契約が自動更新の場合、新たに契約しなおす移行期間は
A: 移行期間は各社が届出で設定する実施日までとなる。(最長11月1日まで)
Q8. 令和5年8月の運賃見直しにより、上限額の概念が無くなったので今後はどんなに高い運賃になろうとも基本的には審査対象とならないということか
A: 貸切バス事業の現状を踏まえると、個々の貸切バス事業者が著しく高い運賃を設定したとしても、競争原理が働くことにより旅客の利益を阻害することにはならないことから、審査対象にはならない。
Q9. 運送引受書の様式改正後、上限額の記載のある様式を継続して使用することは可能か
A: 様式については、告示で定めることとする(令和6年4月1日施行)。告示施行後については、原則新様式を使用することととするが、システム改修が間に合わないなどやむを得ない理由がある場合は、旧様式を使用しても良い。ただし、旧様式を使用する場合は、混乱を招かないよう、利用者に対しその理由を説明するとともに、記載内容を工夫するなどの配慮が必要となる。
Q10. 運輸局による公示から、貸切バス事業者による届出、新運賃・料金の適用までの期間は
A: 令和7年9月26日に公示された運賃・料金に係る届出については、令和7年9月26日から10月24日の期間に届け出を行い、11月1日までの間であれば任意の日から適用することができる。
Q11. 「検討」「調査」に変更した理由は
A: 行政手続法上、届出には「審査」という概念がなく、運輸局等が実施するのは届出内容を受けて変更命令を行うか否かの「検討」、「調査」を行うことになるので、記載を変更することとした。
Q12. 「下限額」を「基準額」に変更した理由は
A: 地方運輸局が公示する額は、各貸切バス事業者が届け出た運賃額が変更命令の発動を要するものであるか否かを判断するための基準であるため、「基準額」としている。また、各貸切バス事業者が届け出る運賃は「下限額」であり、表現の適正化を図ったものである。
Q13. 年間契約の届出をしている事業者が新運賃に契約変更した場合、再度年間契約の届出は必要か
A: 年間契約書に変更が生じた場合には、改めて届出が必要である。
Q14. インバウンドにかかる臨時営業区域の設定を行う際、改めて当該設定にかかる運賃・料金を変更した旨を届出を提出してもらう必要があるのか
A: 公示運賃の見直しがあった場合、インバウンドにかかる臨時営業区域において適用する運賃・料金に変更が生じるが、適用できる運賃は本来の営業区域で届け出た運賃か、隣接区域においては当該隣接区域を管轄する運輸局長が公示する運賃のいずれかであり、運輸局は運賃・料金が変更されることは把握できることから、臨時営業区域において適用する運賃・料金について改めての届出は不要である。
Q15. なぜ車種区分を変更したのか
A: 中型区分に属する一部の車両について、車両価格は小型区分相当であるにもかかわらず、車両長や旅客席数がわずかに小型区分から逸脱していること及び小型区分において、車両価格が異なるマイクロバスタイプの車両(コースター等)とバンタイプの車両(ハイエース等)が同じ車種区分となっていることから、コストに見合った運賃設定ができないケースが存在していた。そのため、改めて車両価格をもとに精査し、「小型車の定義の見直し」及び「コミューター区分の新設」を行うこととした。
Q16. 令和6年3月1日に公示された運賃においては、経過措置が設けられていたが届出は必要か
A: 令和6年3月1日に公示された運賃料金に係る届出については、令和5年8月の公示運賃の見直しから短期間で公示運賃を変更することによる利用者への影響を考慮し、令和7年9月26日の運賃改定までの間、事業者の裁量により、届出を行わないことも可としていたが、今回の運賃の届出において、コミューター車を使用する場合は当該車種区分の運賃を届け出る必要がある。また、コミューター車を使用する場合であって、事業計画を変更していない場合は、事業計画変更届出書を新運賃・料金の実施日までに提出する必要がある。
Q17. なぜ公示運賃の見直しを行ったのか
A: 貸切バスの公示運賃については、原則として2年ごとに見直すこととしている。新たに公示した運賃・料金は、運転者の担い手不足を解消する観点から賃金水準を全産業平均給与額まで引き上げるための原資を確保するため、見直しを行ったものである。
Q18. 今後は公示運賃見直しにかかる要素別原価調査票は不要となるのか
A: 令和7年度から貸切バス事業者に対しては毎事業年度、原価報告書の提出が義務付けられている。公示運賃見直しに係る要素別原価調査については、輸送実績報告書と原価報告書の内容で足りるため、次回の運賃改定では、要素別原価調査は実施しない予定である。
②割引・割増
Q1. 下限額以上であれば相対で決まることになるため、「割引」の設定は不要ではないか
A: 割引の適用の有無は、事業者の判断であり、割引を適用する場合は割引くことができる限度を示す必要があるため、標準適用方法に「届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする」と定めているところ。なお、割引を適用しない場合については、独自の適用方法を設定することになるが、割引を適用しないことは事業者の減収にはならないことから、運賃の割引を適用しない場合についても、標準適用方法と同様の扱いとして差し支えないこととする。
Q2. 割引を適用しない事業者が標準運送約款を適用している場合、第12条の削除に係る独自運送約款の変更認可申請は必要か
A: 必要である。
Q3. 学生、身障者割引運賃の割引率の記載が削除されたのはなぜか
A: 割引の適用の有無及び割引率の設定は事業者の経営判断に委ねられるべきものである。なお、割引を行った結果下限額を下回ることは、運賃・料金制度の趣旨を没却することになるため、届け出た下限額を下回る割引はできないこととする。
Q4. 教育旅行に関しては、積算運賃から更に学生割引を適用するのか
A: 標準適用方法を適用することを前提とするならばそのとおり。但し、届け出た下限運賃を下回ることはできない。
Q5. 交替運転手の料金の22時から5時というのは出庫、入庫する時間も含まれているのか
A: 交替運転者配置料金は、深夜早朝運行料金の時間帯に点呼・点検を行う場合を含めて、収受するものである。
Q6. 深夜割増などの料金(額)は届出時に設定するのか
A: 深夜割増運賃、交替運転者配置料金、特殊車両割増料金は適用方に明示して届出いただく。また、ガイド料、宿泊料等は届出の必要はない。
Q7. 休息期間8時間以上確保できるフェリー乗船の場合、運行後、前の点検時間の2時間は加算できるか
A: フェリー乗船により運行を終了する時点における乗務後点呼時間及びフェリー下船により運行を開始した時点の乗務前点呼点検時間の2時間を加算できる。
Q8. 交替運転手の配置基準は、事業者の社内規定もあるので、合意した中で交替運転手料金を収受することは可能か
A: 交替運転者の配置基準より厳しい基準を設けている場合において、発注者と合意して収受することは問題ない。
Q9. 最初から交替運転手を配置せず、途中で乗務員を交替してワンマン運行を行う場合は交替運転手料金はどのように収受するのか
A: 交替運転者が交替地点まで車両に同乗せず、別の交通手段で交替地まで向かった場合は、当該交替運転者を拘束する対価として運行の出発地から車両に同乗したものとみなして料金を適用するものとする。一方で、営業所を複数設置している事業者において、運行途中にある営業所で運転者の交替を行うなど、実質的に交替運転手の拘束が発生しない場合は交替運転者配置料金は収受すべきではない。
Q10. 運賃額は下限額以上であれば相対で決まることになるため、「割増」の設定は不要ではないか
A:
- 深夜早朝割増
バス事業者として収受しなければいけない料金であるため、現行の2割以内ではなく2割とする。 - 特殊車両割増
運賃算定原価には高価な車両に係る減価償却費も含まれ、平均化されてしまっているため、高価な車両出運行する場合は料金として追加費用を収受する必要がある。なお、新たなサービスの創造を促す観点から、現状の標準適用方法における「5割以内」の規定は削除する。 - 交替運転者
バス事業者として収受しなければいけない料金であり、独自運賃を適用した事業者においては、届け出た下限額以上で料金を設定する必要がある。
Q11. 特殊車両割増料金において、上限は撤廃されたとの認識で差し支えないか
A: 特殊車両割増料金の上限は撤廃されたという認識で差し支えない。当該割増率については、事業者が車両価格等をもとに決めるものであるため、国が審査するものではなく、事業者が利用者に対して理解を得られるよう説明すべきものと考える。
Q12. 割引について割引率の記載が削除されているが、各団体に異なる割引率を適用してもいいか
A: 割引については、適用の有無は事業者の判断であることから、個々の運送における割引率についても、経営状況等を鑑み適切に設定されたい。
Q13. 端数が生じることになるが、四捨五入してよいのか
A: 深夜早朝運行料金に一円単位の端数が生じたとしても、四捨五入をしない。運賃・料金については、算出された運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めて算出する。
Q14. バス事業者の自社都合で、中型だったものが大型になった場合は追加運賃になるか
A: 利用者保護の観点から、自社都合の場合に追加運賃を請求することは適切ではないと考える。
③経過措置
Q1. 新運賃・料金を適用するにあたっての経過措置
A: 新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっても、従前の運賃・料金による額を適用することができる。
ただし、予約や合意の内容に具体性がなく、運行時期や運行内容等が特定できないようなものは有効なものとは言えないと考える。
なお、従前の運賃・料金を適用する場合は、監査の際に従前の運賃を適用したことを監査官に説明できるよう、運送引受書に予約内容がわかる書面も併せて保存しておく必要がある。
【令和7年9月の公示運賃改定に係る修学旅行等の特例措置】
新たな運賃・料金の実施日以後、令和9年3月31日までに実施される修学旅行等にかかる旅行のバスの手配については、新たな運賃・料金の実施日前日までに学校側と旅行業者との間で旅行を催行する旨の合意がなされている場合であって、かつ、貸切バス事業者と旅行業者との間で契約を締結する際に、貸切バス事業者が当該旅行にかかる運送について従前の運賃・料金を適用することを了承した場合には、上記に定める「合意」があったものとして経過措置の対象とすることができる。
なお、これに該当する運送を引き受けた際は、当該運送であることがわかる書面(受注型企画旅行申込書、手配依頼書等)を運送引受書とともに保存することとする。
Q2. 届出の実施日前の契約で従前の運賃を適用できる経過措置の期間はどのくらい先までの期間で可能か
A: 新運賃・料金の実施日以前に従前の運賃・料金にて契約が締結されている運送については従来の運賃・料金が適用されることは言うまでもないが、長期契約の場合、社会的経済的事情を踏まえて契約内容を見直すことができる旨の条項が盛り込まれていることもあるので、契約の相手方と新運賃・料金への移行について協議することが望ましいと考える。
Q3. 従前の運賃で契約したもので、届出後に日付、コース等が変更になった場合、新たな運賃料金になるのか
A: 当初契約日を基準として経過措置を適用して差し支えない。なお、運送申込書/運送引受書を再交付しなければならないような変更である場合には、新運賃により計算するべきである。
Q4. やむ負えず他社のバス事業者へ代車をした際に、契約が新運賃変更前に契約した仕事であった場合の対応
A: 発注者と運行するバス事業者との間で新運賃による運送申込書/運送引受書を交付し直すべきである。当日の予期せぬ故障等、真にやむを得ないケースについては、利用者保護の観点から、新運賃との差額負担は本来運行する予定であったバス事業者が負担するべきである。
Q5. 学校行事として行われる修学旅行等で、催行の直前で他のバス事業者へ庸車を依頼する場合
A: 本経過措置の対象となる催行であれば、運転者不足等の事由により催行の直前に他のバス会社へ庸車を依頼した場合であっても、庸車の依頼先の事業者が了承すれば、従前の運賃・料金を適用できる。
④運賃の適用方法
Q1. 自社で営業所が数か所あり、実際の運行が契約した営業所から変更になった場合の対応
A: 複数の営業所から回送運行する場合においては、実際の運行に沿った運送引受書を交付することが原則であり、遠方の営業所から回送する場合も、当該車両の回送時間、距離も含めて算出するものとする。ただし、当日の予期せぬ故障等、真にやむを得ないケースについては、バス会社が負担すべきと考える。(運送引受書の備考欄にその旨を明記する。)
Q2. 受注時における計画にて運賃契約し、実際の旅程が著しく変更された場合、差額請求できるか
A: 現行の標準運送約款においても、第19条に基づき精算が可能であり、この取扱に変更はない。しかし、回送区間においては、貸切バス事業者と利用者の間で、変更後の金額の妥当性について、合意形成が困難なケースがあることから、当日の道路状況その他の事由により運賃及び料金に変更を生じたときは、追加請求を行わない旨を標準運送約款に明記している。
Q3. 故障などで、別のバス事業者へ運行をお願いした場合に追加となる回送に係る運賃は、誰が負担するのか
A: 当日の予期せぬ故障等、真にやむを得ないケースについては、利用者保護の観点から、追加となる回送運賃は本来運行する予定だったバス事業者が負担すべきと考える。また、標準運送約款上も、当日の道路状況その他の事由により運賃及び料金に変更を生じたときは、追加請求を行わない旨を標準運送約款に明記している。
Q4. 申し込みの行程に対する計算上のキロ数、時間で誤差はどの程度認められるか
A: 恣意性を排して作成した行程(例:一般的に使われている地図アプリや運行管理ソフト等を用いたうえで、一般的に想定される渋滞を意図的に考慮しないといったことをせずに作成した行程)であれば、実際の運送とキロ数、時間が多少異なっていても問題ない。ただし、行程作成時と異なるルートを走行したり、渋滞等に巻き込まれたことによりキロ数、時間に変更が生じた場合は当然精算の対象となる。
Q5. スクールバスなどの朝・夕のみの運行の場合、利用しないで待機する時間は拘束時間から排除すべきか
A: 待機した時間は時間制運賃を収受する。ただし、改善基準告示でいう休息期間を与えた場合には、当該時間は走行時間から除くことが出来る。
Q6. スクールバスで午前3時間、午後3時間で日中は車庫に戻る運行は、どう算出するのか
A: スクールバス運送は、学校などの児童生徒等の登下校時に運送され、かつ、登下校時の間に帰庫するという運送形態を踏まえ、1日に行われる当該運送を1つの運送として以下の計算方法により適用することができる。
<時間制運賃の計算>
- 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下、「点呼点検時間」という。)として1時間ずつ合計2時間と、登校及び下校時の走行時間(登校時及び下校時の運送の出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。)を累計した時間とを合算した時間に1時間当たりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、登校及び下校時の走行時間を累計した時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間とする。 - 走行時間の端数については、点呼点検時間と累計した走行時間を合算した時間に30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げること。
<キロ制運賃の計算>
- 登校及び下校時の走行距離(登校時及び下校時の運送の出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。)を累計した距離に1キロ当たりの運賃額を乗じた額とする。
- 走行距離の端数については、累計した距離に10キロ未満は10キロに切り上げること。
<運賃額>
- 運賃は車種区分別に計算した金額の下限額以上とする。
- 運賃は営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算する。
<その他>
- 年間契約通達によりスクールバスの年間契約を締結する際には、本回答で示す計算方法を適用することができる。
- 児童生徒等の登下校時に運送され、かつ、登下校時の間に帰庫するというスクールバスの運送形態と本質的に同様の形態であれば本回答で示す計算方法を適用することができる。
Q7. 仕事をかみ合わせた場合の回送の考え方
A: 仕事をかみ合わせたことにより、運送申込書/運送引受書がどのように記載されることとなったのか、その記載内容により収受すべきである。詳細な計算方法については原文をご参照ください。
Q8. 宿泊を伴う運行の運賃の計算方法は
A: 宿泊場所到着後1時間、翌日の宿泊場所出発前1時間ずつを、点呼・点検時間として時間制運賃に加算する。点呼・点検時間を除く宿泊中は、休息時間として運賃計算の対象とはならないが、宿泊に伴う実費料金は収受すべきである。
Q9. 日帰りの遠足等で中抜けになる仕事の算出方法
A: 待機した時間は時間制運賃を収受する。ただし、改善基準告示でいう休息期間を与えた場合には、当該時間は走行時間から除くことが出来る。
Q10. 2泊3日の運行で、中日は全く運行せず、乗務員がホテルで待機している場合、中日の時間制運賃は収受できるのか
A: 運転者が乗務・運行せず、ホテルで単に待機している場合は、中日の時間制運賃は収受できない。なお、中日の運転者拘束に係る実費相当額を収受することは差し支えない(届出不要)が、料金表を明示する等、発注者に説明した上で収受願いたい。
Q11. 実際に10円単位で四捨五入となっているが、運賃表示は必要か
A: 公示運賃により届出を行う場合、運賃表示は10円単位となる。ただし、下限運賃で計算した額を下回らなければ、千円以下切り捨て等で請求することは差し支えない。
Q12. 契約時の運行キロ、時間が運行後大幅に乖離があった場合の考え方
A: 現行の標準運送約款においても第19条に基づき精算が可能であり、この取扱に変更はない。なお、恣意性を排して作成した行程(例:一般的に使われている地図アプリや運行管理ソフト等を用いたうえで、一般的に想定される渋滞を意図的に考慮しないといったことをせずに作成した行程)であれば、実際の運送とキロ数、時間が多少異なっていても問題ない。
Q13. 故障などでやむを得ず代車した場合に、回送キロなどが当初お客様と契約したものよりオーバーした場合
A: 当日の予期せぬ故障等、真にやむを得ないケースについては、利用者保護の観点から、追加となる代車の回送運賃は本来運行する予定だったバス会社が負担すべきと考える。(運送引受書の備考欄にその旨明記する。)
Q14. 夜行、両夜行の場合の仮眠時間については、運賃に入れるのか
A: 運送の待機時間中に仮眠を取るのであれば時間制運賃を収受することとなり、交替で運転する場合は交替運転者配置料金を収受することとなる。
Q15. 受注の際は旅行会社からおおまかな行程表がきて、見積もりを行い受注する場合、最終行程と誤差が生じた場合
A: 時間・キロ併用制運賃計算方式では、運送申込書に運賃計算が可能となる行程が記載されなければ計算はできないため、まずは計算が可能となる行程を求めていくべきである。発注者の事前の経路変更によって大幅に時間・距離が変更となる場合ついては、変更契約を行うべきである。
Q16. 乗合車両の貸切流用の場合も同様の運賃料金の算出方法でよいか
A: そのとおり。
⑤旅行会社との取引
Q1. ガイドなどの実費料金から旅行会社が手数料を収受することはできるのか
A: ガイド料など貸切バス業者が立て替えただけの実費に対して貸切バス業者が旅行業者等に手数料等を支払っている場合は、道路運送法第9条の2第1項の運賃料金変更事前届出違反に該当する。
Q2. 旅行会社の手数料に関して法的な縛りはないのか。手数料を上げれば現状の運賃と変わらなくなる
A: 手数料の収受については当事者間の契約によるものであり、それ自体が問題になるものではないが、安全を阻害する過大な手数料については運賃の割り戻し違反に該当する。
具体的には、令和7年6月に貸切バス業者に義務付けた原価報告書を基に契約運賃から手数料等の額を控除した結果、当該報告書に基づく一運送に必要な安全コスト額を下回っている場合、運賃の割戻しの対象となる。
Q3. 手配旅行において、旅行会社がバス事業者と契約した運賃以上の運賃をお客様へ提示し、収受することは問題ないか
A: 旅行会社が、手配旅行において、貸切バス事業者が契約時に運賃として提示した金額を増額し、運賃として旅客に請求することは想定されない。なお、運賃に手数料を付加して旅行代金として旅客に請求することはあり得る。
Q4. 旅行会社の運賃違反の罰則の具体的内容は
A: 貸切バス事業者の届出運賃違反について、旅行業者の関与が疑われることから、物流・自動車局から観光庁に通報した場合、旅行業法に基づき立ち入り検査等を行い、違反があれば行政処分を含めた対応が行われると承知している。
Q5. 運賃を守るために国の監査を強化してもらえるか。監査は徹底されるのか
A: 貸切バス事業者の届出運賃違反について、旅行業者の関与が疑われることから、物流・自動車局から観光庁に通報した場合、旅行業法に基づき立ち入り検査等を行い、違反があれば行政処分を含めた対応が行われると承知している。
Q6. 旅行会社の年間契約の考え方
A: 届出により審査対象運賃とするが、弾力的に審査する基準を示したところ。
⑥行政の入札
Q1. 入札時に詳細な行程が決まっていないものについては、どのように入札すればよいか
A: 運賃計算が可能となる行程を求めることが必要であり、届出運賃に基づく範囲内により計算した入札額にするべきである。
Q2. 入札等で同業者として下限割れの疑いが生じた場合に相談・通報等窓口は設置されるのか
A: 最寄りの運輸局等又は運輸支局等に相談されたい。
Q3. スクールバスなどの自治体との契約運送などの運賃が急激にアップすることへの対策
A: 白バス行為については、従前から警察と連携して取り締まりを行っているところであり、引き続き対策に取り組んでいく。
Q4. 地方の行政にお願いされ、採算割れしても協力し続けて観光バスを運行しているが、新運賃になるともう不可能か
A: 自社が届け出た運賃・料金にて運行されたい。
Q5. 行政からの委託で安価な実証実験での運行をお願いされた場合はどう対応すればよいか
A: 自社が届け出た運賃・料金にて運行されたい。
Q6. 入札等で下限割れ運賃で落札した事業者があった場合、入札し直しを訴えることはできるのか
A: 入札し直しができるかどうかはコメントする立場にない。
⑦その他
Q1. 新高速乗合バスの受託をしているが、新たな運賃料金になった場合はどちらの運賃で算出すればよいか
A: 委託料については、その算出方法等を示す書類の添付を求めることとしているが、貸切バスの公示運賃を根拠として委託料を算出することを妨げるものではない。
Q2. 出庫から入庫までで運賃計算を行うが、出発地から遠い事業者ほど運賃が高くなり、相見積もりで不利になってしまう
A: 本制度は運行にかかる経費を元に運賃を算定することとしているため、出発地から遠い事業者ほど、経費、そして運賃が高くなることはやむを得ないと考える。なお、営業所の新設は自由に行えることから、事業を経営するうえで必要であれば営業所の新設を検討されたい。
Q3. 労使協定の中で、従業員の冠婚葬祭でバスを利用する際に、特別運賃を定めている
A: 自社内の話であり、当該事業者の判断に委ねるべきと考える。
Q4. 旅行会社を兼業するバス事業者は、包括旅行で契約の際、新運賃制度を遵守しない抜け道になるのではないか
A: 貸切バス事業者は、運送申込書/運送引受書に記載の運賃・料金を収受することとなる。
Q5. 改正運輸規則第7条の2第3項の「その額を記載した書類」の具体的内容は
A: 手数料額が確認できる書類を保存しなければならない。なお、手数料額には手数料率も含むものとする。詳細な保存方法については原文をご参照ください。
記事について
本記事は、運輸局の公式通知に基づいた貸切バス運賃料金制度のQ&A集です。制度全般から運賃適用まで、7つのセクションにまとめられています。各質問をクリック/タップすると詳細な回答が表示されます。
ご不明な点については、最寄りの運輸局等にお問い合わせください。