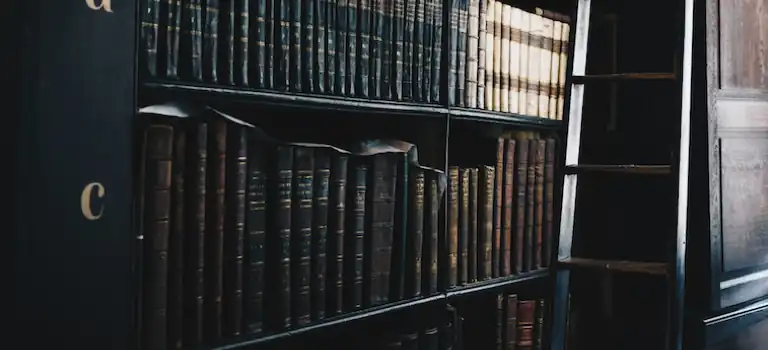バス運転者の改善基準告示Q&A|拘束時間・休息期間の完全ガイド
令和6年4月から適用された改善基準告示について、バス運転者の労働時間管理に関する重要なQ&Aを厚生労働省の公式資料に基づいて詳しく解説します。拘束時間、休息期間、連続運転時間などの実務上の疑問点を網羅的にカバーしています。
法的根拠
根拠法令:改善基準告示(令和6年4月1日適用)
出典:厚生労働省労働基準局監督課「改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A」(令和5年3月)
⚠️ 本ページの情報は公式資料に基づいていますが、実際の運用にあたっては必ず最新の法令・通達をご確認ください。法的判断が必要な場合は、運輸局または労働基準監督署にご相談することをお勧めします。
改善基準告示とは
改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)は、自動車運転者の労働条件の向上を図り、もって交通の安全の確保及び運転者の健康の保持を目的として定められた基準です。
令和6年4月1日から新たな基準が適用されており、バス運転者の労働時間管理において、より厳格な遵守が求められています。本ページでは、実務上よくある疑問点について、厚生労働省の公式Q&Aに基づいて解説します。
主要な基準(バス運転者)
- 1か月の拘束時間:281時間まで(特例:年間3,300時間、1か月最大310時間まで)
- 1日の拘束時間:原則13時間以内(最大16時間、15時間超は週2回まで)
- 休息期間:継続9時間以上
- 運転時間:2日平均で1日当たり9時間以内
- 連続運転時間:4時間以内
1. 拘束時間・休息期間に関するQ&A
改善基準告示が適用されないバス運転者は?
改善基準告示は、事業場を異にする場合を除き、同一の使用者に使用される労働者の全員について適用されるため、以下の場合には改善基準告示は適用されません。
適用されない例
- 1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場では44時間)を超えない範囲内で、日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
注意:上記以外の、いわゆるパート労働者、アルバイト等を含むバス運転者については、改善基準告示が適用されます。
1か月の拘束時間281時間の起算日の扱いは?
1か月の拘束時間の起算日は、特定の日を定め、その日から起算して4週間(28日間)又は1か月間(暦日によるもの)のうち、いずれか短い期間において281時間を超えない範囲内とすることとされています。
したがって、これらのうち、事業場単位で起算日を定めることが必要です。
具体例
例えば、1月5日を起算日と定めた場合:
- 1月5日から2月1日までの4週間(28日間)
- 1月5日から2月4日までの1か月間(31日間)
このうち、短い期間である28日間において281時間を超えないようにする必要があります。
1か月の拘束時間310時間の「年間6回まで」の年間の起算日は?
改善基準告示における「年間」については、毎年4月1日を起算日として翌年3月31日までの期間とされています。
重要:労働基準法第36条第1項の協定における「1年」の起算日とは異なる場合があるため、注意が必要です。
労働時間等の「設定改善」には何が含まれるのか?
労働時間等の「設定改善」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
設定改善の具体例
- 所定労働時間の短縮
- 年次有給休暇の取得促進
- 週休2日制の導入・定着
- 連続休暇の取得促進
- 勤務間インターバル制度の導入
- 働き方・休み方の見直し
拘束時間に含まれない「荷待ち時間」はバス運転者にも適用されるか?
荷待ち時間に関する改善基準告示の規定は、トラック運転者に係る規定であり、バス運転者には適用されません。
バス運転者については、荷待ち時間に相当するような時間は想定されず、荷待ち時間の規定を設けていません。
参考:トラック運転者の場合、一定の要件を満たす荷待ち時間は拘束時間に含まれないとされていますが、バス運転者の労働実態を考慮し、このような規定は設けられていません。
1日の拘束時間15時間超は「週2回まで」だが、週の起算日は?
「週」については、日曜日から土曜日まで又は月曜日から日曜日までといった特定の曜日を定めて起算することとし、その起算日はバス事業者において定めることとされています。
注意点:起算日を定めずに、単に日曜日又は月曜日の到来する度にそれぞれの曜日を起算日として取り扱うことは、改善基準告示の趣旨に反します。
具体例
事業場で「月曜日」を起算日と定めた場合:
- 月曜日0時から日曜日24時までが「1週」となります
- この期間内に15時間を超える拘束時間の回数が2回以下であることが必要です
休息期間を2分割する場合、「8時間以上の継続した休息期間」の考え方は?
休息期間を2分割する場合の「8時間以上の継続した休息期間」とは、休息期間を分割することとした場合の、分割された一方の休息期間については、連続して8時間以上でなければならないという趣旨です。
具体例
✓ 適切な例
8時間の休息期間 + 1時間の休息期間 = 合計9時間
✗ 不適切な例
7時間の休息期間 + 2時間の休息期間 = 合計9時間
(いずれの休息期間も8時間未満のため不可)
重要:休息期間は原則として継続9時間以上とすることが必要ですが、宿泊を伴う長距離運転等の場合に限り、一定の条件の下で分割することができます。
休息期間を分割する場合、フェリー乗船時間も分割の一方として認められるか?
休息期間の分割については、自動車運転者が業務の用に供される自動車に乗車しないことを条件としているところ、フェリー乗船時間は業務の用に供される自動車に乗車しているため、原則として休息期間の分割の一方とすることはできません。
例外的な取扱い
ただし、以下の要件を全て満たす場合は、フェリー乗船時間を休息期間の分割の一方として取り扱うことができます:
- フェリー内に、運転者が身体を伸ばして休息することができる設備(ベッド等)があること
- フェリー内の当該設備を、運転者の所属する事業者が確保していること
- フェリーの運航が、運転者が通常どおり予定している次の勤務の開始に影響を及ぼさないこと
- フェリー内での休息時間について、「1日についての拘束時間」の計算に当たり、フェリー乗船時間の2分の1を「拘束時間」に算入すること
参考:上記の要件を満たさない場合、フェリー乗船時間は全て拘束時間として扱われます。
休息期間に労働者が自由に利用できない仮眠時間は休息期間に含まれるか?
休息期間は、バス運転者が労働から離れることを保障されている時間であり、この「労働から離れることを保障されている」とは、使用者の拘束を受けないことをいいます。
仮眠時間(仮眠を含む休憩時間)は、労働から離れることを保障されているか否かにより、以下のように判断されます:
✓ 休息期間に含まれる場合
バス運転者が労働から離れることを保障されており、自由に利用できる仮眠時間である場合、休息期間に含まれます。
✗ 休息期間に含まれない場合
バス運転者が労働から離れることを保障されておらず、自由に利用できない仮眠時間である場合、休息期間には含まれません。
例:警報や電話等に対して直ちに対応することが求められている場合など
注意:実態として労働から離れることが保障されていない仮眠時間は、拘束時間に含まれることになります。
2. 連続運転時間に関するQ&A
連続運転時間4時間の中断として認められる「運転以外の作業」とは?
連続運転時間の中断として認められる「運転以外の作業」とは、原則として荷役作業、点呼を受けることその他の運転以外の作業に従事し、かつ、原則として休憩(仮眠を含む)している場合をいいます。
「運転以外の作業」の具体例
- 点呼を受けること
- 荷役作業(バス運転者の場合は該当しないことが多い)
- 休憩(仮眠を含む)
該当しないもの
単に車両を停車させているだけで、以下のような行為は「運転以外の作業」には該当しません:
- 信号待ち
- 渋滞中の停車
- 駐車場での待機時間(単なる待機)
連続運転の中断時間として、1回当たり「おおむね連続10分以上」とは?
「おおむね連続10分以上」の「おおむね」とは、運転以外の作業及び休憩の時間等については、一定の幅をもたせ、その都度、運転日報に記録し、後日確認できるようにすることで足りるという趣旨です。
具体的な時間の考え方
「おおむね連続10分以上」とは、5分以上15分未満の範囲内であれば許容されるという趣旨ではありません。
運転者の生理的欲求に配慮し、かつ、運転に伴う疲労を回復させるには、連続した運転からの解放が相当程度必要であり、その目安となる時間として10分を基本としています。
実務上の取扱い
やむを得ない理由により、1回当たりの運転の中断時間が10分を若干下回る場合であっても、以下の要件を満たす場合は「おおむね連続10分以上」として取り扱うことができます:
- 運転日報に記録し、後日確認できること
- 常態化していないこと
「原則として連続10分以上」の「原則として」の意味は?
「原則として」とは、連続運転時間の中断について、1回当たりおおむね連続10分以上であることを原則とするものの、少なくとも30分以上運転を中断する場合は、1回当たりおおむね連続10分以上でなくとも差し支えないという趣旨です。
具体例
✓ 許容される例
5分 + 5分 + 20分 = 合計30分の中断
(合計30分以上であれば、個々が10分未満でも可)
✗ 認められない例
5分 + 5分 + 5分 = 合計15分の中断
(合計が30分未満の場合は、各回10分以上が必要)
注意:この例外はあくまで合計30分以上の中断を取る場合に限られます。30分未満の中断の場合は、原則通り1回当たりおおむね連続10分以上が必要です。
Q13-Q14の詳細も同様の形式で表示されます
3. 予期し得ない事象への対応に関するQ&A
「予期し得ない事象への対応時間」とは
運転中に予期せず発生した一定の事象(車両故障、フェリー欠航、災害・事故による道路封鎖、異常気象等)への対応時間については、一定の要件を満たす場合、拘束時間・運転時間・連続運転時間の計算から除外することができます。
Q15-Q20の詳細も同様の形式で表示されます(6項目)
予期し得ない事象の具体例、除外できる時間の計算方法、客観的記録の保存方法などを解説
4. 2日平均の運転時間に関するQ&A
2日平均の運転時間の起算点は、特定日の始業時刻の24時間前から48時間か、特定日の前日の始業時刻から48時間か?
運転時間は、特定日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましいですが、特定日の最大運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、以下の両方の平均で判断されます:
判断基準
- ① 特定日(N日)の運転時間と特定日の前日(N-1日)の運転時間との平均
- ② 特定日(N日)の運転時間と特定日の翌日(N+1日)の運転時間との平均
→ いずれもが9時間を超えた場合、初めて違反と判断されます
計算例
特定日の前日(N-1日)が10時始業、特定日(N日)が11時始業の場合:
- ① 特定日の前日の始業時刻(10時)から起算して48時間で計算
- ② 特定日の始業時刻(11時)から起算して48時間で計算
上記①②のいずれもが9時間を超えた場合、改善基準告示違反と判断されます。
結論:したがって、特定日の前日の始業時刻から48時間で計算することとなります。
まとめ
令和6年4月から適用されている改善基準告示は、バス運転者の労働条件改善と交通安全の確保を目的とした重要な基準です。本Q&Aでは、拘束時間281時間の計算方法、休息期間9時間の確保、連続運転時間4時間の遵守など、実務上頻繁に疑問が生じる事項について解説しました。
特に注意が必要なのは、「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いです。車両故障や災害による道路封鎖などが発生した場合、一定の要件を満たせば拘束時間等から除外できますが、客観的な記録の保存が必須となります。
貸切バス事業者の皆様におかれましては、本Q&Aを参考に適切な労働時間管理を行い、運転者の健康確保と安全運行の両立を図っていただくことをお勧めします。ご不明な点がございましたら、運輸局や労働基準監督署にご相談いただくか、当事務所までお気軽にお問い合わせください。